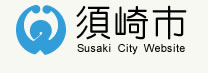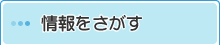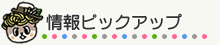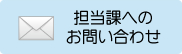固定資産税
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の土地、家屋、償却資産(これらを固定資産といいます)の所有者に対して、その価格(評価額)に応じて課税される市税です。
固定資産税は本市税収入の半分以上を占めており、市民サービスを提供するための基幹税目として非常に重要な役割を果たしています。
納税義務者
毎年1月1日現在に固定資産を所有している方であり、具体的には次のとおりとなります。
| 土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
|---|---|
| 家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録している法人または個人 |
※所有者が売買などにより変更された場合でも、1月1日現在において登記簿などの名義変更手続が完了されていない場合には、前所有者が納税義務者となります。
共有名義の場合
土地や家屋が共有名義の場合、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務があります。(連帯納税義務 地方税法第10条の2第1項)
このため、共有者の持分ごと別々に課税することはできないことから、代表者の方に納税通知書をお送りしています。
(参考)【地方税法第10条の2第1項】
共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
納税義務者の方が死亡された場合
土地・家屋の納税義務者が死亡した後の固定資産税については、地方税法第9条の規定により、相続人全員が連帯して納税義務者となり、固定資産税を納付していただくことになります。
また、地方税法第9条の2の規定により、相続人代表者(相続人を代表して納税通知書を受領し、納付していただく方)を相続人の間で決めていただき、相続人代表者となられる方は、「相続人代表者指定届」のご提出をお願いします。
また、未登記の建物については、「固定資産(家屋)未登記物件の相続申告書」のご提出をお願いします。
※「相続人代表者指定届」「固定資産(家屋)未登記物件の相続申告書」は該当する相続人に送付しています。
※この届出や申告によって、法的に相続が確定するものではありません。固定資産の所有権移転については法務局で手続きを行う必要性があります。詳しくは、下記法務省ホームページをご覧ください。
税率
1.4%
課税標準
その固定資産の1月1日現在の価格(評価額)。
1 土地、家屋について
国が定める評価基準に基づき、3年ごとに評価替えを行って評価額が決められます。 このとき決められた評価額は、地目の変換、土地の分合筆、家屋の増改築などがあった場合を除き、原則として3年間据え置かれます。 ただし、地価の下落傾向が見られる地域については、評価額の修正を行います。
2 償却資産について
毎年、個々の資産の取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価額が決められます。
税額の計算方法
課税標準額×税率
※ただし、課税標準額が評価額に対し低い土地については、平成18年度法改正により、負担調整措置が以下のように定められます。
| 商業地等の宅地 | ||
|---|---|---|
| ア | 前年度課税標準額が、当該年度評価額の60%以上70%以下の場合 | 前年度課税標準額を据え置きます。 |
| イ | 前年度課税標準額が、当該年度評価額の60%未満の場合 | 前年度課税標準額に当該年度評価額の5%を加えた額を課税標準額とします。 ただし(イ)により計算した額が、当該年度評価額の60%を上回る場合は60%相当額とし、20%を下回る場合は20%相当額が課税標準額となります。 |
| 住宅用地 (当該年度の評価額に住宅用地特例率(1/6または1/3)を掛けた額と比べて) |
||
| 前年度課税標準額が、100%未満の場合 | 前年度課税標準額に当該年度評価額に住宅用地特例率を乗じた額の5%を加えた額を課税標準額とします。 ただし、計算した額が、当該年度評価額に住宅用地特例率を乗じた額の20%を下回る場合は20%相当額が課税標準額となります。 |
|
住宅用地の課税標準の特例
住宅用地については価格の3分の1(ただし、家屋の床面積の10倍まで)、住宅用地のうち小規模住宅(住宅1戸につき200平方メートルまでのもの)については価格の6分の1を限度に課税標準額を定める特例が設けられており、税額が軽減されます。
免税点
同一市内に同一の人が所有する各資産の課税標準額の合計額が、次の金額未満の場合には、固定資産税は課税されません。
| 資産の別 | 土地 | 家屋 | 償却資産 |
|---|---|---|---|
| 免税点 | 30万円 | 20万円 | 150万円 |
固定資産課税台帳の縦覧
固定資産税(土地又は家屋)の納税者の方が、自己の資産と他の資産の価格を比較できるようにするため、土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載)をご覧いただく制度です。(償却資産については、縦覧の対象ではありません)
家屋評価
- 新築された家屋は評価額(価格)を決めるための調査が必要です。新築された方は税務課までお知らせください。
改築(リフォーム含む)された家屋は、再評価が必要となる場合があります。改築等された方は税務課までお知らせください。
償却資産の申告
償却資産については、土地、家屋とは異なり申告課税となりますので、償却資産を所有しておられる方は、毎年1月1日現在における資産の状況を、1月31日までに当該資産が所在する市町村に申告していただく義務があります。(地方税法第383条)
申告書用紙は、毎年12月中旬に、お送りしています。 事業をされている方で申告書が届かない場合は、税務課へご連絡ください。
償却資産とは
会社や個人で工場、商店およびアパートなどを経営しておられる方や、農業、漁業をされている方などが、その事業のために用いることができる構築物・機械・備品などを、「償却資産」といいます。
【具体例】
- 構築物
看板(広告塔等)、舗装路面、駐車場(周壁がないもの)、緑化設備、庭園、門、塀、堀、側溝、煙突、焼却炉、鉄塔、鉄柱、トンネル、橋、ビニールハウス、カーポート等 - 機械および装置
各種製造・加工設備、印刷設備、ガソリンスタンド設備、土木建設機械(パワーショベル・ブルドーザー)、耕運機などの農機具(車両を除く)等 - 船舶
漁船、貨物船、客船、砂利採掘船、遊覧船、ボート等 - 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等 - 車両および運搬具
大型特殊自動車、構内運搬車等(自動車税・軽自動車税が課税されるものを除く)
大きさが下記の基準に該当し、最高速度が時速15km以下のものは、小型特殊自動車(軽自動車税の課税対象)とされ、固定資産税の対象とはなりません。
長さ 4.70メートル以下
幅 1.70メートル以下
高さ 2.80メートル以下 - 工具、器具および備品
机、イス、ロッカー、応接セット、テレビ、陳列ケース、ルームエアコン、冷蔵庫、各種工具、ファクシミリ、LAN配線、パソコン、コピー機、レジスター、自動販売機等
申告の対象となる資産
賦課期日(毎年1月1日)現在において、事業の用に供することができる資産で、次に掲げる資産も課税の対象となります。
- 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
- 建設仮勘定で経理されている資産および簿外資産
- 遊休または未稼動の資産
- 割賦購入資産で、割賦金を完済していない資産であっても、すでに事業の用に供されている資産
- 取得価格が10万円未満の償却資産であっても、個別に減価償却しているもの
- 福利厚生の用に供するもの
申告の対象とならない資産
- 自動車税または軽自動車税の課税対象となる資産
- 無形減価償却資産(漁業権、営業権、商標権、特許権など)、繰延資産
- 耐用年数が1年に満たないもの(使用可能期間が1年未満のもの)
- 取得価額が10万円未満で、税務会計上、一時に損金の額に算入しているもの
- 取得価格が10万円以上20万円未満で、法人税法上または所得税法上、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うもの
償却資産の評価
取得価額を基礎とし、耐用年数および取得後の経過年数に、価格の減少(減価)を考慮して評価します。
- 前年中取得のもの
取得価額(※1)×{1-(減価率(※2)÷ 2)}=評価額 - 前年前取得のもの
前年度の評価額×(1-減価率)=評価額(※3)
※1 取得価額 事業の用に供する資産を購入したときの購入価格をいいます。機械などの資産で、据付費などを要した場合は、その費用(付帯費)を含みます。
※2 減価率 資産の価値が時の経過によって減少する率で、財務省が定める「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「(別表第7)旧定率法による償却率」と同じものです。
※3 評価額の最低限度 取得価額の5%が最低限度となります。また、耐用年数を過ぎた資産でも、除却するまでは評価の対象となります。
納税の方法
市役所から送付される納税通知書により、年4回に分けて納めていただきます。