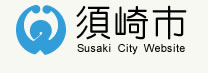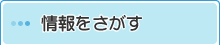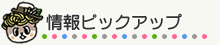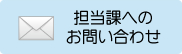概要
須崎市の概要
須崎市は昭和29年10月1日、須崎町を中心に多ノ郷村、浦ノ内村、吾桑村及び上分村の5か町村が合併して市制の施行をしました。 本市の立地は高知県のほぼ中央に位置し、県都高知市から西に約30キロメートルです。
市の西部を流れる清流としても有名な新荘川は、1974年にニホンカワウソの生息が確認されました。 その後、1979年に新荘川で確認されたのを最後に、日本で目撃された事例はありません。
ニホンカワウソ(新荘川にて撮影)
風光明媚な横浪半島に昭和49年に完成した「横浪黒潮ライン」からの眺めは秀逸で、南には土佐湾や太平洋を見渡し、 北に目を転じると静かな浦ノ内湾の眺望が楽しめます。
本市における人口の推移は、合併当時および昭和30年代の初めには約35,000人程度でしたが、 少子高齢化が進行し人口の減少に歯止めがかからない状況が続いています。
横浪半島
本市の主要産業である一次産業の漁業では沿岸漁業とカンパチ、鯛、ハマチなどの養殖漁業などが盛んに行われています。 また、農業においてはハウス栽培によるミョウガ、キュウリ、ピーマン、シシトウ、花卉(かき)などが主要作物です。 特にミョウガ栽培は、全国一の販売額となっています。
ミョウガ
また、須崎港は昭和40年に国の重要港湾に指定されており、貿易港として貨物取り扱い量は県内一を維持しています。 主な取り扱い貨物はセメントや木材が中心となっています。港の入り口には石灰石の積出港があり、 仁淀川町の鳥形山からこの積出港まで24kmの距離を専用のベルトコンベアで運び、ここから全国に向かって搬出しています。 平成14年の「よさこい高知国体」を契機に、高速道路「高知自動車道」が伊野ICから須崎東ICまで延伸し、 人、物の流れのスピード化が図られました。
須崎湾